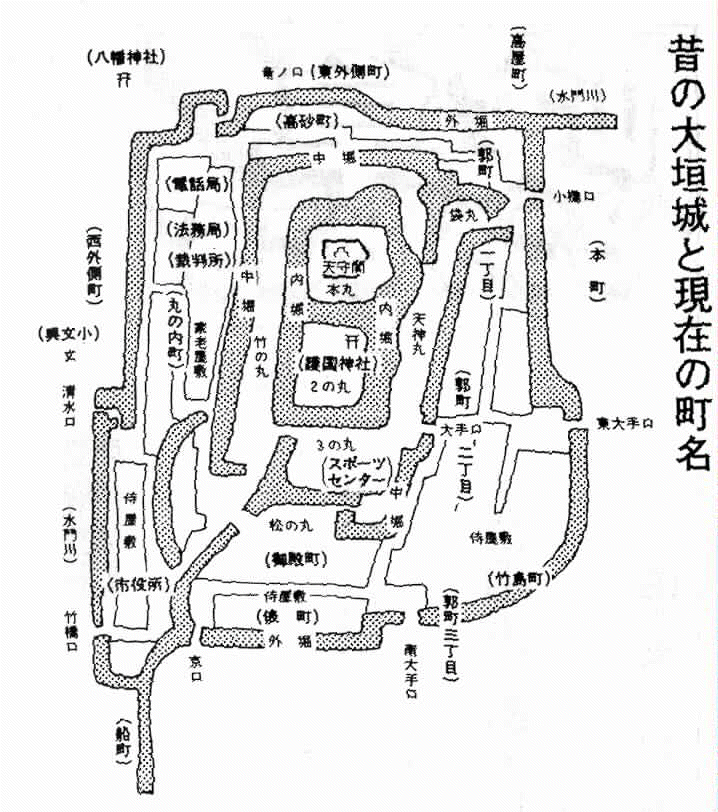
●ここはみなさんと考え、学ぶネットです。地元の声として市民のみなさんにお知らせしたい事・行政にお願い・お尋ねしたい事をお寄せ頂き、支え合う地域社会づくりを。
興文連合自治会
興文学区の町名
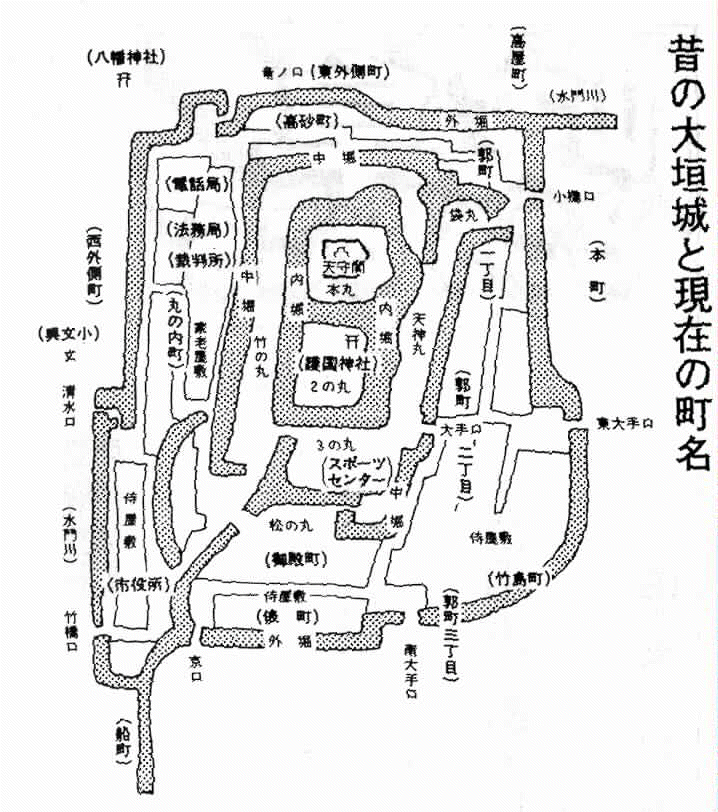
もと大垣城本丸、二の丸、三の丸等が在って御郭内と云われた処は、やがて明治になって元郭内と呼ばれ、商業を営む人々が集まり始めて郭町となり、町並みが発展するにつれ町名改定の際、郭町、御殿町、丸の内、高砂町と名称がさだめられた。
大垣藩校敬教堂の前身は天保時代藩士岡田主鈴が開いた私塾。のち大垣蘭学問所となり、英語・西洋医学・武学・国語・蘭学等を教え、幾多の英才を輩出した。10代藩主氏彬の時、敬教堂の精神的なよりどころとして聖廟が建てられ、そこにモクセイ科のトリネコが植えられ、剣の木と呼ばれていた。大垣大空襲にも傷つきながらも生き続け、現在地東外側町保健センターに植え替えられ、保護されている。
明治時代になって、大垣藩校・敬教堂は武学校と文学校に分けられ、武学校は南校、文学校は北校と呼ばれた。その後、南校は高等小学校になり、今の興文小学校に北校は実科女学校となり、大垣城北にあった高等女学校と共に大垣高等女学校になって、今の大垣北高等学校になった。
郭町 城のかこいを郭といい、大垣城ゆかりの地であることを町名が物語っている。市内の代表敵な商店街。常葉神社、大垣城、大垣公園、大垣城ホールなどあり、市民の憩いの場となっている。
10月の十万石祭りは、常葉神社の例祭で、常葉神社は大垣城旧竹の丸跡の現在地に再建されたもの。
▲大垣城
大垣城築城は、天文4年(一五三五)、宮川安定という。しかし、この城が歴史の舞台に登場したのは関ケ原合戦で、西軍の本拠となってからである。 また、江戸時代から、中山道と東海道を結ぶ重要な美濃路沿いに発展した城下町として注目される。 大垣械は戦国時代の風雲の中で多くの武士の血を浴び、動乱を息づいてきたが、第二次大戦で焼滅し、新たに再現されたもの。
|
郭町東 郭町の東側にある商店街。大手門跡がある。 東外側町 郭内の外にあるので外側町と名付けられた。西流する水門川北岸に沿う地域で、大垣停車場線が南北に走り、水門川と交差するところに水門橋がある。主要地方道の西2丁目が興文校下。保健センター、急患医療センターなどあり、大垣藩校敬教堂跡、トリネコがある。 桐ケ崎町 城下町時代には侍町であったといわれている。商店街。 西外側町 東から西へ曲流する水門川西岸の住宅街。両外側町とも、御郭内の外にあるので外側町と名付けられた。興文小学校、円通寺、八幡神社などがある。なお、興文小学校校庭には、小原鉄心の胸像あり。 番組町 寛永元禄年間に侍町となり、藩御用の番匠に属する者の屋敷があったので、この名がある。 鷹匠町 番組町同様寛永元禄年間に侍町となり、此処に住む藩士は城主の鷹狩に随従する鷹匠であったので、この名がある。 西長町 寛永元禄の頃、侍町となり東長町に対し、町並が長いので、この名ある。 馬場町 北境に大垣運河が東流する住宅地。大垣藩士の馬場があったので町名になった。寛永年間には馬場の両側の大部分に藩士の屋敷があったという。 船町 中央を県道岐阜垂井線が東西に貫通し、東部を南流する水門川との交点に高橋がある。県道の北側、水門川西岸沿いに2丁目、その南、県道に沿って4丁目があり、2丁目と4丁目の一部が輿文校下。商店・住宅街であるが、この地は史跡・文化財が豊富で、水門川の船町港跡には住吉灯台がある。松尾芭蕉の奥の細道むすびの地として市史跡にも指定され、谷木因俳句道標が連てられている。曹洞宗全昌寺(2丁目)境内には幕末維新の勤皇家・小原鉄心の別荘無何有荘(市文化財)がある。 ▲奥の細道むすびの地 神田町 西大垣停車場線が中央を東西に貫通し、西端の近鉄西大垣駅に通じている。商店・住宅地。 室村町 室村の一部が木戸町2丁目、鳩部屋町、西崎町、室本町、室町、宮町 見取町になつた。室村町はもと室宇といい大井荘内、元徳2年(一三三〇)の東大寺名寄帳に見える。当村に往古より室清水があったという。 見取町 東西に走るJR東海道本線をはさんでいて、興文校下は3ー4丁目。東大寺文書に見取と見える地名あり。 宮町 文明年間に既に存在していた町名のようである。 室町 正徳時代の明細帳によれば、室村に室町があり八幡神社北と西の地域で、江戸初期より侍屋敷となった。 西崎町 興文中学校、西崎水源池などある。承応年間牛屋村を西崎村と改称している。西崎村は明治初め、切石村に編入、まもなく分村独立し、昭和16年から西崎町と呼ぶようになったという。 鳩部屋町 番組町と同様、寛永元禄年間に侍町 室本町 旧商業高校跡地にスイトピアセンター、図書館、文化会館などがある。室村の地域は、北は今の宿地町に当り、南は牛屋村(西崎村)の北端辺であったといわれている。室村5丁目から11丁目が名称変更されて室本町ができた。住宅地。 木戸町2丁目 都市計画復興土地区画整理事業によりできた住宅地。 参考文献 昭和35年発行大垣市立興文小学校120年史編集 興文120年史、地域文化研究会の著書等参考にて記述 |

生活情報支援ネットワークと共に市民に活力パワーの創造を提供します。