Ⅰ.きものの名称言えますか
まず何より、きものの構成を覚えましょう。きものは平面的、直線断ちなので、
その分要素が多く名称も数多くなります。これらをしっかり知っておくことに
よって、人に着付けてもらうにしても自分で着るにしても、着こなしに差が出て
きます。図1のうち、着付けの際よく使われる名称は、おくみ 剣先(けんさき)
褄(つま) 身八つ口(みやつぐち) 共襟(ともえり) 衿肩あき(えりかたあき)
・・・など。後の章で出てきますのでしっかりチェックしておきましょう。
図1
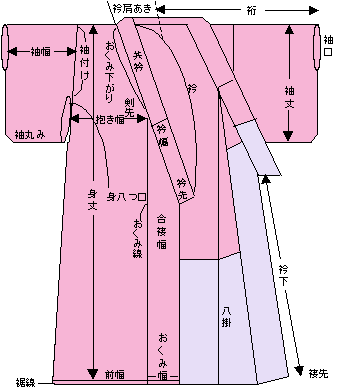
Ⅱ.サイズを正しく計りましょう。
身丈は長着(きもの)そのものの長さで、つまり身長とほぼ同寸です。
着丈は図2のように首のぐりぐりから足首までの長さ。身丈と着丈の差は、
後で説明します「おはしょり」になります。
図1の前幅に当たる部分の寸法です。
腰まわり × 1/4 + 2cm を目安にします。
ただし、腰まわりは一番ふくよかな部分を計りましょう。
同じく後幅に当たる部分です。
腰まわり × 1/4 + 8cm を目安にします。
袖が身頃についている部分に当たります。背の低い人など帯の位置を高く
する人は21cm、背の高い人や太目の人など帯の位置の低い人は24cm位が
目安です。
※また、きものの場合は、長さの単位として尺や寸を使うことがあります。
一尺=約38cm,一寸=約3.8cmです。
Ⅲ.アイテムのいろいろ
例えば洋服に、きちっとしたフォーマルウェアもあれば、カジュアルなセーターや
パンツがあるように、きものにもそれぞれの持つ「格」によってアイテムのタイプが決
まっています。
ここでは、洋服とは違いミスかミセスによって、はっきり区別されているものなども含
めた「約束ごと」を紹介していきます。
Ⅲ-1.アイテムのいろいろ[ミス編]
ミスの慶事の第一礼装。花嫁が着る本振袖と成人式なので着る中振袖、小振袖の総称
です。柄は一面に模様が配置された総模様づけで絵羽模様です。
豪華さだけでなく若々しさを演出する、「今、着て欲しい」アイテムです。
略1礼装の一つです。柄は絵羽模様ですが振袖より自由で、肩から裾にかけて模様づけ
された肩裾模様が多いようです。ミスの人でも少し落ち着いた気分を味わいたいなら、
訪問着に紋をつけると、格が上がり振袖に匹敵します。
模様が全て上向きに配置され、略式の訪問着です。絵羽模様ものと、小紋との中間的
なきもので、普段着としても使用でき広範囲に着られます。
洋服の「カジュアルな外出着」にあたり、きもの全体に同じパターンの小さな模様が
つけられた柔らかい生地のきものの総称です。格式ばらず気軽に装えるので、パー
ティーやクラス会、コンサートやちょっと気取って食事など、応用範囲の広いきもの
です。小紋のもつ独特の「優しさ」を大切にしたいですね。
若々しく清楚なハカマ姿は、歩きやすく行動的です。成人式、卒業式など若い時に
経験する節目節目に、厳かに装いたいアイテムです。
晴着の略礼装として中振袖を合わせる他、色無地一つ紋、付下げ、小紋などとも
相性がいいようです。
Ⅲ-2.アイテムのいろいろ[ミセス編]
ミスの振袖に対してミセスの慶事の第一礼装。
地色は黒で、染抜き五つ紋付の江戸褄(えどづま)と呼ばれている裾模様を配したき
ものです。仲人や婚礼のおよばれなど、改まった席にふさわしい大変格式高いもの
です。
地色が白地や色地で裾模様がついたもの。紋の数によって格式が少しずつ違ってき
ますが、ほとんど公式の礼装として通用します。
お嫁入りの時の訪問着が少し派手になったと感じたら、落ち着いた色柄の訪問着が
似合う年頃。
装飾もソフトなイメージにして、気品溢れる装いを楽しみましょう。ミセスならで
はの初々しい社交着です。
広範囲に着られるきものですから、帯は用途に合わせて、袋帯、名古屋帯など自由
に着こなしてみてはいかかでしょうか。
色無地一つ紋は慶弔両方に着られる略礼装で大変重宝します。
格式のある席なら、上品な色のきものと模様のある袋帯を合わせて、少しくだけた
席には、名古屋帯と合わせてコーディネートしましょう。また紋のない場合は、お
しゃれ着として広く利用できます。お茶席などには最もふさわしいきものですが、
ミスの人でもハカマに合わせるなどして装えるもっとも応用範囲の広いアイテムの
ひとつです。
外出着として広く用いられる小紋ですが、中でもおとなしくつつましやかな江戸小
紋は、落ち着いたミセスに似合うアイテムです。これも紋の有無や帯によって略礼
装や外出着にも利用します。
Ⅳ.季節ときもの
日本には、独特の四季風情が有ります。同じようにきものにも、柄や色や生地
に表現される季節感を感じることができます。ここで紹介する、季節やTPOに合っ
た装い方を、きものを着る基礎知識としてしっかり覚えましょう。
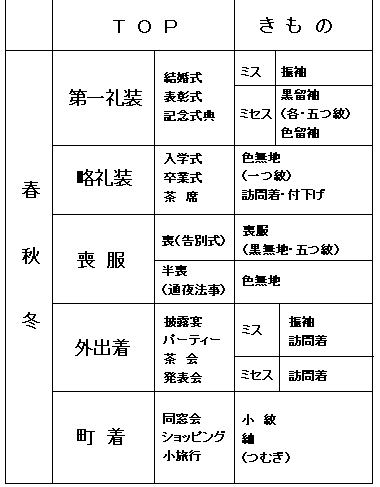
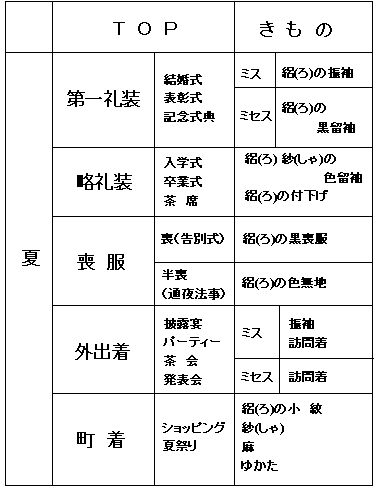
Ⅴ.小物と役割
一番下に着る肌着。夏は汗取り、冬は保温と通気の役割を果たします。
吸湿性のある木綿などの素材がてきしています。
肌じゅばんの上に着る長じゅばんや長着のウエスト部分の上に締める幅広いもの。
衿元、胸元を整え、着崩れを防ぎます。
腰から下に巻きつける下着。きものの裾が痛むのを防ぐとともに、保温をも兼ねます。
きものの丈の調節や胸元をととのえるために巻きます。最近では素材に伸縮性が有り、
ワンタッチで滑り止めにもなる物があります。
帯枕をつつむと同時に帯ときものの間をつなぐ重要な役割を果たすものです。きものや
帯との調和のよい色・素材を選んで、帯の上にふっくらと出したり、中に入れてしまっ
たりして着こなします。
結んだ帯がとけないように締めるひもです。幅が広く太いものや金銀入りは礼装用、
幅が狭くうすいものは、街着として使います。帯じめは、着こなしの締めくくりでも
ある大切な小物です。
くるぶしの後は、金具で止めるようになっています。足袋の白さは足元の美しさを
いっそう引き立てます。外出時には、替え足袋を一足持ち歩くといいでしょう。
実践編
Ⅰ.着物を着る前に・・・
どんなきものを着るにしても、まずこれを準備すること。
きもの一式<肌じゅばん・裾よけ・長じゅばん・伊達締 2本・帯板・帯枕・足袋・
腰ひも 3本~4本・帯あげ・帯じめ>補正用具類・小物類・草履・バック・持ち物(
ハンカチなど)は、前日までに点検し、着るときは並べておきましょう。(長じゅばん
に付ける半衿やきものに付ける伊達衿は、あらかじめ付けておきます。)
また、着る場所は整えて、出来れば敷紙の上で着用します。ヘア・メイクは先に済ませ
ておき、手を洗い直して時間に余裕を持って着たいものです。
〔着つけの前に済ませるアレ・コレ〕
◆トイレを済ませる
きものを着てしまってからでは、着くずれが心配です。また外出先と時刻の確認も
必要です。ただし、途中で気分が悪くなっても最近は着脱の便利なランジェリー小物
がありますから、日によって使い分けるのがいいでしょう。
◆足袋を履く
帯まで結び上がってから履くのでは着くずれしやすいので、足袋は肌着の一部と考え
て一番先に履きます。腰をおろし、足袋を半分に折り返してから履けば履きやすいで
しょう。
◆カラダの補正を行う
平面的に構成されたきものに適している体型は、円筒形に近いものです。
なだらかな肩や胸元、ウエスト部分の適度なくびれを、市販の補正パットやコルセッ
ト、タオルなどを使って補正し、まず土台作りです。
Ⅱ.着物を着る時に・・・
|